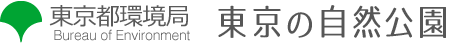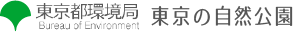大島の動植物
ワオキツネザル
東京都立大島公園の一部である動物園には、噴出した溶岩をそのまま生かした国内最大級のサル山があり、サル山にはマダガスカル島の固有種ワオキツネザルがいます。原産国では、川沿いの林や乾燥林、サバンナ、岩場など多様な環境に生息しています。他のキツネザルの仲間と比べて地上にいる事が多く、数頭から30頭程度の群れで生活しています。群れでは、オスよりもメスの方が上位です。4~5月頃に1~2頭の子供を産みます。

バーバリーシープ
噴出した溶岩を利用したワオキツネザルとバーバリーシープの放飼場は、1周約300mと国内最大級の大きさを誇り、そこでは様々な方向から動物を観察できます。バーバリーシープは、ヒツジとヤギの中間のような外見で、赤茶色か黄褐色の毛は、首から肩にかけて短く、上を向いたたてがみがあります。また、喉と胸と前肢の上部には、長くて柔らかい毛があります。岩場や切り立った崖、砂漠、乾燥林など過酷な環境に生息しています。
二ホンイタチ
伊豆大島のニホンイタチは日本固有の在来種ですが、伊豆諸島南部のイタチは、ネズミを駆除するために放たれた国内移入種です。オスとメスで体の大きさが異なり、オスの方が大きく成長します。敵に襲われたり、驚いたりすると、肛門の脇にある臭腺から臭い液体を出します。年に1回、春頃に繁殖期を迎え、1度に1~8匹(平均4~5匹)出産します。子育てはメスだけで行います。

カラスバト
大島公園動物園のフライングケージは、巨大空間の中に池や湿地帯、丘陵地帯等の地形が作られおり、日本でも屈指の大きさを誇ります。フライングゲージでは、カラスバトをはじめ、群れをなすフラミンゴ、カモ、オシドリ、クジャクなど、主に15種の鳥達が棲んでいます。カラスバトは、日本の天然記念物に指定されており、1回の繁殖で卵を1つ産みます。伊豆大島にも野生のカラスバトが生息しており、「グゥー」という鳴き声が聞こえたら、素敵な出会いがあるかもしれません。
アオウミガメ
大島の人気地形スポット、ケイカイの水深10mから20mのエリアではかなりの高確率でアオウミガメが見られます。アオウミガメの大きさは80cm~100cm、重さは70kg~230kgととても大きく、ほかのカメと違って海草を食べて生活する草食動物です。ケイカイは、非常に入り組んだ複雑な地形と山脈のような根なので潮通りが良く、特に冬から春にかけては一度に数個体を目の前で見ることも多く、カメ好きにはオススメです。

回遊魚たち
まばゆいくらいに輝く、碧い海に囲まれている伊豆大島。黒潮の恵みを受ける伊豆大島では、釣り人たちが憧れるマダイ、イシダイ、シマアジ、イサキ、メジナカサゴなど、様々な魚が生息しています。海の中を覗くと、自由に泳ぎ回る魚がたくさんいます。そんな魚達を狙えるのが、知る人ぞ知る伊豆大島の魅力です。仕掛けを落とせば、魚が釣れる。入門者やファミリーで魚釣りを楽しむことができます。

桜株(さくらっかぶ)
オオシマザクラの巨木。樹齢800年以上と推定され、伊豆大島で何度も起こった噴火の中を生き残ってきました。幹から何本もの木が生えているように見えますが、もとは一本の大木。その高さ2mから上は枯れてしまいましたが、倒れた太枝は生きていました。その枝が地面に根を張り、地上にヒコバエを出して新しい幹となったのです。今でも毎年春に満開の花を咲かせます。倒れてもまた美しい花を咲かせるその姿には、不屈の生命力が宿っているようです。国の特別天然記念物に指定されています。
オオシマザクラ
オオシマザクラは桜の原種で、伊豆大島を代表する自生種のサクラです。島中の至るところにあり、その数は180万本といわれています。新緑の季節の4月初めに、山がひととき白い洋服をまとうような美しい光景が見られます。北東部の泉津地区の山中にあるサクラ株は、樹齢は推定800年といわれています。なお、エドヒガンとオオシマザクラの交雑種は、一般的に知られるソメイヨシノであるといわれています。
ヤブツバキ
いわずとも知れた伊豆大島で有名な植物といえば、ヤブツバキです。元々、ヤブツバキは多く自生していましたが、伊豆大島の土壌は火山灰を多く含み水はけが良く、島では強い風が吹く土地柄、防風林として数多く植林されました。さらに椿油の原料としても植林され、今では伊豆大島にはヤブツバキが300万本あるといわれています。島中がヤブツバキだらけです。
オオシマツツジ
庭先や公園に植えられているオオシマツツジは準固有種です。本州などに自生しているヤマツツジと比べ、花芽や花冠が大きく、花の色が鮮明です。4月中旬から5月終わりの間に、大島の至る所で見ることができます。また、大島温泉ホテル内にあるつつじ園は素晴らしく綺麗で、一見の価値があります。
お問い合わせ
このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。