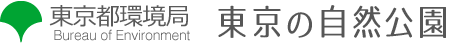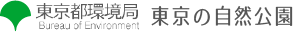父島の歴史
小笠原諸島発見(ボニンアイランド)、捕鯨文化と最初の移住者
小笠原は、およそ200年前まで無人島であったため、「ぶにんしま」と呼ばれ、英語圏では小笠原諸島のことを、ボニン・アイランド(Bonin Island)と呼びます。「小笠原」という地名は、1593年に信濃国の武士であった小笠原貞頼が発見したという言い伝えからきています。19世紀の太平洋は捕鯨活動が盛んで、その中でも小笠原近海は欧米の捕鯨船団に人気がありました。1830年、捕鯨船に水と食料を供給するために住み着いた欧米人と太平洋諸島民が最初の定住者となりました。
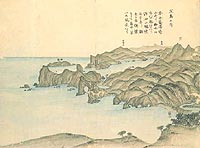
(C)小笠原村
戦時中の疎開と戦後の日本への返還
小笠原は、江戸幕府や明治政府の調査と開拓により 1876年(明治9年)に日本領土となり、大正から昭和初期にかけては、亜熱帯性気候を生かした農業・漁業により、人口は7000人を超え、栄えました。しかし、太平洋戦争により、ほとんどの島民は本土に強制疎開を命じられました。戦後は米軍の統治下におかれ、それから23年後の1968年に、小笠原諸島は日本に返還されました。1979年に村政が確立され、自然と共生する村をめざし、現在に至っています。

(C)小笠原村
お問い合わせ
このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。