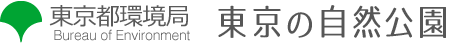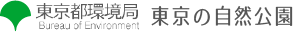母島の歴史
小笠原諸島発見(ボニンアイランド)、捕鯨文化と最初の移住者
19世紀の太平洋は「捕鯨船の時代」といわれるほど捕鯨活動が盛んで、ハワイ、ニュージーランドに並び、小笠原諸島は欧米の捕鯨船団に人気の海域でした。人が最初に定住したのは、江戸時代後期の1830年、欧米人と太平洋諸島民でした。その後、江戸幕府や明治政府の調査と開拓によって、1876年に日本領土となりました。小笠原諸島は無人島であったため、「ぶにんのしま」と呼ばれました。英語圏では、小笠原諸島のことを「ボニンアイランド(Bonin Island)」と呼びます。その名の由来は、ぶにん→Bunin→Boninと言われています。
(C)小笠原村
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/history/(外部サイト)
![]()
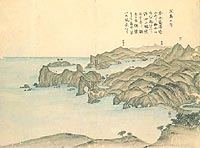
戦時中の疎開と戦後の日本への返還
太平洋戦争が始まる前の1920年以降、山の多い父島と母島に砲台がつくられ、陸軍や海軍が多く配置されました。1944年、日本軍は米軍との戦いで住民が足手まといになると考え、一般住民全員を内地に強制疎開させました。翌1945年、硫黄島での米軍上陸作戦の末、日本軍は敗退し、小笠原諸島は米軍統治下に置かれました。戦後23年が経った1968年、小笠原諸島はようやく日本に返還されました。2018年に返還50周年を迎えますが、耕されていた農地が原生林化しているなど、73年間の歴史空白期を抱えたまま、現在に至っています。

(C)小笠原村
お問い合わせ
このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。