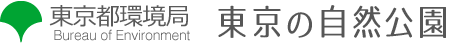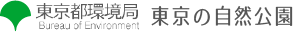檜原・あきる野の動植物
クマタカ
山地の広葉樹林を生息地にしていて、小さなネズミ類からタヌキ、ヤマドリなどの動物を食べています。クマタカはトビよりもひとまわり大きく、日本では昔から、オオタカなどとともに、鷹狩りに使われる種として有名です。
https://foundation.tokyu.co.jp/environment/wp-content/uploads/2012/12/200.pdf(外部サイト)
![]()
オオルリ
オオルリは夏鳥で、檜原村の山の渓流沿いでよく見られます。オスは、濃いブルーの背と、白い腹のはっきりしたコントラストの色合いで、とても目立ちます。高い木のこずえなどで、長時間、場所を変えず、尾を振りながら高く澄んだ美しい声で「ピールーリー」とさえずります。メスは地味な色彩で、巣は崖や岩のすき間のため、見つかりにくいです。
http://www.hinohara-mori.jp/content/gallery_bird.html(外部サイト)
![]()
キビタキ
キビタキは、南から日本に渡ってくる夏鳥です。よく繁った落葉広葉樹林にふさわしい、黄色と黒色のコントラストが鮮やかな色合いと、明るく大きな鳴き声が特徴です。林の中を飛び交いながら、餌の虫をとっています。オスはカラフルですが、メスは地味な暗緑色をしています。ヒタキ科の鳥であり、胸の色の黄色からキビタキと名付けられたといわれています。
http://www.hinohara-mori.jp/content/gallery_bird.html(外部サイト)
![]()
コマドリ
コマドリは、ほぼ全国の山地の森林に棲んでいる夏鳥で、檜原都民の森をはじめ、檜原の森で見ることができます。生息期間は、4月下旬から9月下旬です。「ヒンカラカラカラカラ・・・」という鳴き声が馬のいななきに似ていることから、駒(=馬)鳥と名付けられたといわれています。全長14cmほどで、オス・メスともよく似た色彩です。
http://www.hinohara-mori.jp/content/gallery_bird.html(外部サイト)
![]()
カタクリ
檜原村の春を代表する山野草で、御前山はカタクリの群生地として知られています。開花時期は3月から4月ですが、御前山は標高が高く気温が低いため、4月中旬から下旬に咲くことが多いです。カタクリは、ピンク色の花が下向きに咲くのが特徴です。日中、陽が当たると花弁が反り返り、花弁が大きく開きます。曇った寒い日や雨の日は開花しにくいデリケートな花ですが、曇っていても温度が高めであれば開花します。
シダレザクラ
都心や東京近郊では、桜の花の見頃は3月末ですが、檜原村は標高が高く気温が低いため、見頃は4月の1週目の終わりから3週目の初め頃です。中でも一押しは、武蔵五日市駅からバスで50分ほどの人里(へんぼり)バス停に咲く枝垂れ桜です。レトロな木造の三角屋根の待合小屋に覆い被さるように咲き、バス停は桜に埋もれ、見る人の心を和ませてくれます。「乙津・龍珠院」のシダレザクラも人気です。

秋川渓谷沿いのサクラ
秋川渓谷のソメイヨシノ、光厳寺のヤマザクラなど、秋川渓谷の周辺には多彩なサクラが咲きます。光厳寺のヤマザクラは、樹齢推定400年を超える大きな桜です。見頃の4月上旬から4月中旬までの短い期間には、貴重な開花を愛でるために、多くの人が秋川渓谷を訪れます。

三頭山(みとうさん)のブナ林
三頭山には、東京都では貴重なブナ林があります。東京都内で、まとまって残っているブナ林は、三頭山と日原川流域だけといわれています。ブナ林の林床にはササ類が密生することが多いですが、三頭山のブナ林にはササ類が少ないため、学術的にも注目されています。林床には、ミヤマハコベ、チゴユリ、コチャルメルソウのような花も咲きます。
お問い合わせ
このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。
関連リンク
檜原・あきる野
- 檜原・あきる野の公園の特徴
- 檜原・あきる野の歴史
- 檜原・あきる野の動植物
- 檜原・あきる野の観光
- 檜原・あきる野のアクセス